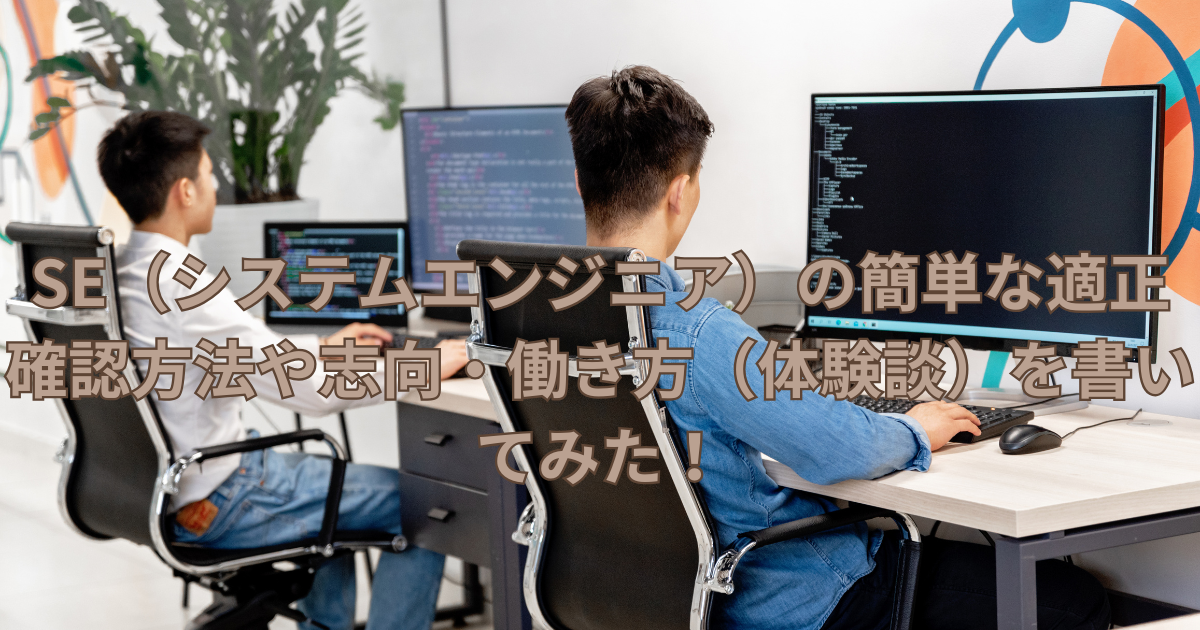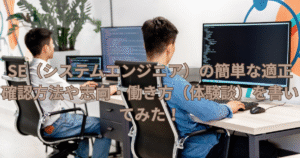職業の選び方は誰もが迷うところですよね。
特にまだ働いたことのない新卒の方には、とても悩ましい所だと思います。
キッザニアのように、就職する前に、職業を気軽に体験できるような世の中だったら、本当にいいのになと思っています(笑)。
新卒時は例えば、絶対大企業とか、福利厚生が充実しているなどを考慮して、企業選びをする方が世の中的に見て多いかと思いますが、社会人になって、働く中で企業選びや見え方はまた、大きく変わってくると思います。
これから未経験でシステムエンジニアを目指される方・IT業界を志望する方。SEについて「どんな仕事を普段するのかな」、「私には適正があるかな」など迷われている方へ、私の主観になってしまいますが、ここに少しでもヒントを書けたらと思います。
ここでいうシステムエンジニア(SE)は、ウォーターフォール開発に携わるエンジニアを想定しています。
一次受けの企業は、業務であまりプログラミングを使わないことが多い(むしろ管理やマネジメントがメイン)と思いますが、やはり技術には詳しい方が有利だと思いますので、そういったことを踏まえてこちらに感じたことを記したいと思います。
システムエンジニアの簡単適性確認方法4選
基本情報技術者試験の勉強が楽しいと思えるか(合格できそうか)
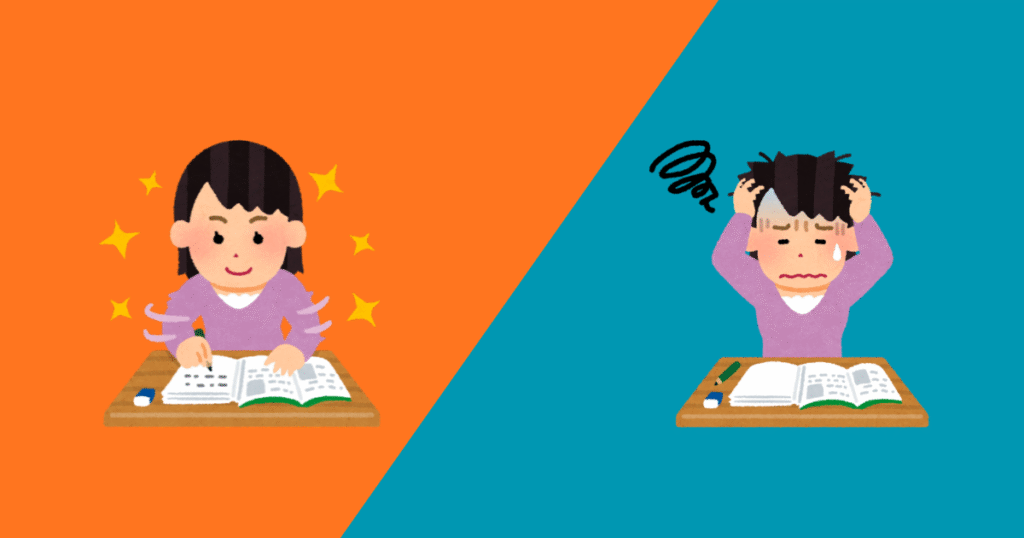
システムエンジニアを目指す方には基本情報技術者試験を取ることが会社でも推奨されるところが多いと思います。
SEは人よりも機械を好きになったり、機械に愛着を持てる方が向いている傾向にあると思っています。
基本情報技術者試験は機械やプログラムについて、学ぶ試験ですので、この学習が楽しいと思える方は、適正があると言えると思います!
本業でも基本情報技術者試験で学習したような内容や基になる考え方が、求められてきます。
機械(コンピュータ)やプログラムがどのように動いているのか、頭の中でイメージ・想像できる方は、設計書を読み込む時や人に何かを説明する時に、自分が納得をしながら、説明することが可能です。
技術的な内容をしっかりと理解しながら、プロジェクトを推進できる方は、とても頼られることが多いと思います。
説明をする際は、技術的な内容+コミュニケーション力が求められるので、コミュニケーション力があれば、どうにかなるという話ではないと感じています。
そのため、しっかりと機械、プログラミング、ITなどの領域や学習に拒否反応が出ないか事前に見極めておけると、入社後のギャップは少なくできます。その確認として、基本情報技術者試験はとてもうってつけだと思います!
近年科目B(午後問題)の問題でアルゴリズムが必須の出題範囲になり、その独特な考え方も好きになれるか確かめてみると良いかもしれないです!
本屋の本棚(コンピュータ、プログラミング、IT)の本を見て、もっと読みたいと思えるか

ITの世界は、自発的な学習が求められる業界です。なので、興味を持てないと、正直自分自身が苦しくなってしまうと感じています。
そこで、本屋の本棚のIT系の棚を見渡して見て、本棚の前で長時間立ち止まったり、実際に買って読んでみようと思えるか。それとも興味がわかなかったり、直ぐに本を閉じたくなってしまうのか、一番簡単に興味関心がわかる方法だと思います。
また、ITの本棚だけではなく、仕事にありそうな全体の本棚のジャンルを見渡して、興味を持てたジャンルを探してみても良いかもしれません。
ITの本棚より、興味や関心の惹かれたジャンルがあるということは、それがあなたにとって心が動く、ジャンルや職業である可能性が高いです!
プロゲートをやって、プログラミングにアレルギーがないか確認
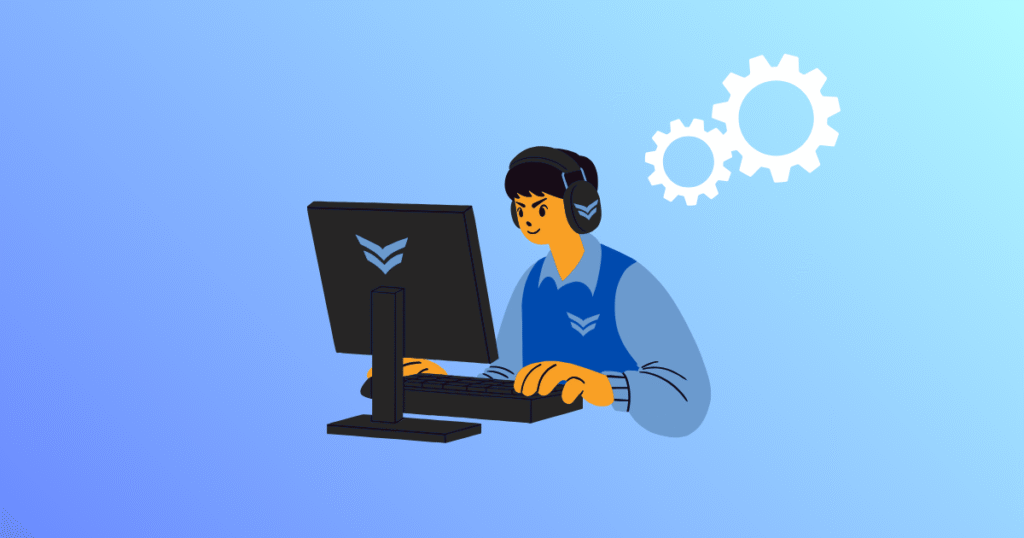
プログラミングの適正を図るには、プロゲートというサイトがあります。
ここで、まず実際に自分の手で動かしてみて、楽しいと思えるか確認しておくと、向いているのか判断がつきます。
楽しくて、ハマる人はプロゲートを一通りやった後、自分で何かアプリケーションを開発するなどの、能動的な気持ちが湧いてくると思います。この気持ちが持てる人は、エンジニアに非常に向いていると思います。
SEは基本的にものづくりの方なので、ITで何かアプリケーションを作ることや動かすことが苦手じゃないことが大切です。プログラミングはその基になるものなので、プログラミングにアレルギー反応が起きないか事前に判断できると良いです!
中学・高校時代の科目である「情報」が好きだったか
学問をより抽象化して、昔の記憶から考えてみるのもおすすめです。
中学・高校時代に情報という科目があり、PCの前で授業を受けたかと思いますが、
あの授業や教科書の内容、PCでの制作やプログラミングが楽しいと思えた方は、適正がある可能性が高いです。
SEの仕事は基本、オフィスや自宅を出ずに、PCの前に座って、長時間作業をするお仕事です。
情報の授業もそんな感じだったかと思いますが、「PCの前でカタカタ作業をするより、外で体育してたいんじゃー」という方は、おそらく営業や外回り向きです。
また、基本的な内容を理解し、習得している方は、難しいことが出てきても、基礎の考え方を応用して、対処できる可能性が高いです。基礎の時点で、つまらなかったり、楽しめていない場合は、難しい内容で躓く可能性が高いです。
昔の自分は情報が好きだったのか、それよりももっと好きな科目が他にあったのか考えてみると良いかもしれません。
ChatGPTを使えば、昔の好きな教科から向いている職種を推定してくれるので、好きな教科と相関がある職種を選べば、仕事で学ぶことも苦ではなくなる可能性が高いです!
実際に業務を通して感じた志向・働き方(体験談)
正解が1つの業務が好き

システムエンジニアの業務は、基本、誰が行っても最終的には、正解が同じ(1つ)にならなければいけない業務です。そのため、自分のオリジナリティなどは発揮しづらい職種です。
マーケティングや広告などは、正解が決まっていないので、試行錯誤しながら、最適なものを考えて、検証していくことが必要ですが、SEはそういったことはないと思っています。
その代わり、技術やノウハウなどのルールを勉強し、学んだことを活かして、自分の力で、問題やエラーを解決していくことにやりがいを感じる方には向いています。
間違いやエラーが頻繫に出る環境なので、それを嫌がらずに、1つの正解にたどり着くのが楽しいと思える方は、向いています。正に数学で、1つの解答にたどり着いた時の感覚に近く、それを楽しいと思えるかが大事です。
チームプレーと個人プレーは4:6くらいの割合

システム開発は個人単位でできる仕事ではないので、プロジェクトを推進する上で、チームプレーは欠かせません。
自分が与えられたタスクをこなしつつも、メンバーと連携しながら、エラー箇所をつぶしたり、連携して業務を取り組む箇所は多いです。
個人作業は多いですが、日頃からチームでコミュニケーションを取りながら、業務を正確に進めていくことが大切です。開発スケジュールは決まっているので、後戻りが発生しないように、チームメンバーと確認する作業が都度発生します。
そうした会議やコミュニケーションが発生しない時間以外は自分のタスクを進めるといった感じです。その時間帯は完全個人作業で、自分のタスクを黙々と進めていきます。
会話がなく、1人でずっとパソコンに向き合っても、苦にならない
基本的にパソコンの画面とにらめっこで闘うので、結構疲れている時は、心に来ます(笑)。
エラーなどがあったときは、何が原因でエラーになっているのかひたすら考えられる原因を試して、探ることになります。
また、PCがあれば、基本的にどこでも仕事ができるので、リモートワークやフルリモートがしやすい職種です!
それはとても嬉しいのですが、人とのコミュニケーションが少なくなり、孤独感は少し感じます。
実際にSEはうつ病の患者さんが多いようです。
厚生労働省が発表している「業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況」によると、全業種の中で「情報通信業・情報サービス業」は5番目に精神障害の請求件数が多い業種となっており、高めの順位になっています。
そのため、1人で悩みや問題を抱え込みすぎないことが大切です。
逆に、会社に出社したら人間関係をめんどくさく感じたり、1人の方が全然集中できるという方はあまり気にしなくてて大丈夫です!
プロジェクトによって、残業時間が変わっても気にしない人
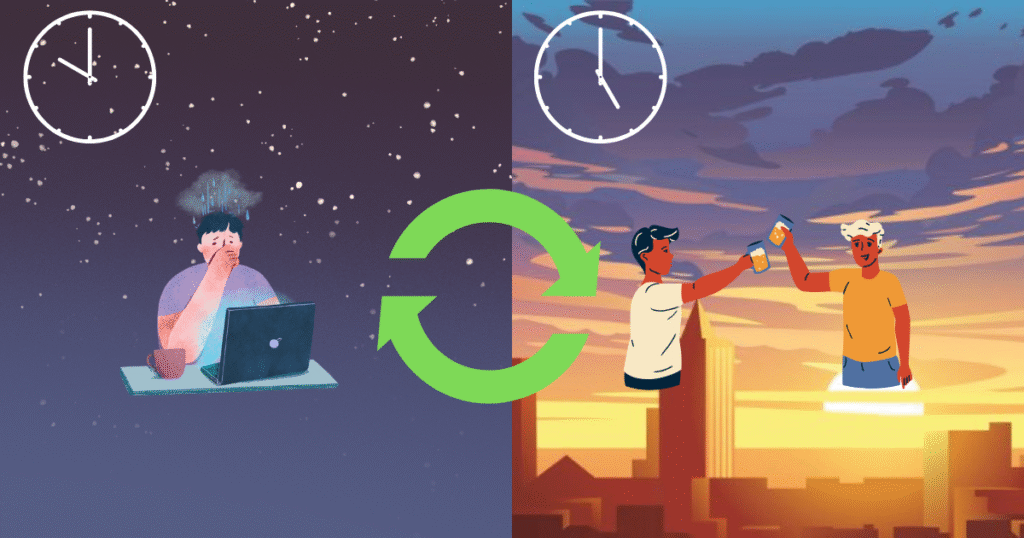
世間一般的には、銀行員や公務員、メーカーの方は、基本的に残業があまりなく、日々の忙しさが一定のような職業であるイメージです。
しかし、システムエンジニアは、コンサルティング職のように、プロジェクトによって大きく残業時間が変化していきます。それはチームの人の能力や事前のプロジェクト計画によって大きく異なるからです。
忙しくないプロジェクトなら定時帰り、炎上案件に入れば、スケジュール通りに間に合わせるために、残業や業務時間が伸びてしまいます。もちろんその分、その期間は、残業代をしっかりと稼ぐことができます。
意外にも、持続力や体力が必要な職業なので、プロジェクトによって残業時間は変わるんだと認識しておきましょう!